2017年6月28日
おしゃれ料理小説『パンとスープとネコ日和』で異彩を放つのは「頭脳パン」
ヤミー編集部からオイシイ情報をお届け!!
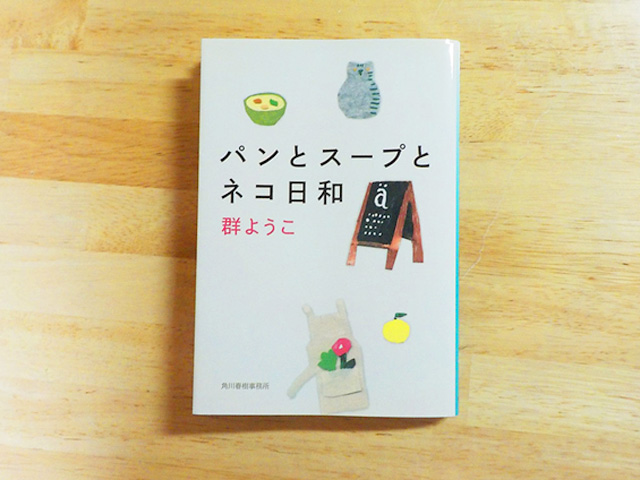

『かもめ食堂』好きにおすすめ・おしゃれ料理小説『パンとスープとネコ日和』
「おしゃれ料理小説」と言ってしまうと語弊があるかもしれませんが、『かもめ食堂』の群ようこさんの作品なので、やはりそんな雰囲気の小説です。ドラマ化の際には、主演が小林聡美さんだったし、安定のもたいまさこさんだったし、映像化してもやはりそんな雰囲気でした。
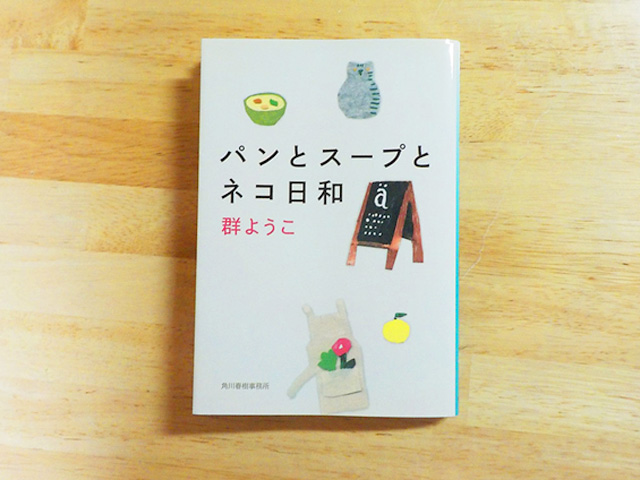
主人公のアキコは53歳。たった一人の身内であった母親を亡くし、勤めていた出版社を退職して母親が長年営んでいた昔ながらの食堂を改装。“ボリュームのあるサンドイッチとスープ、サラダの、オーソドックスなメニュー”を提供する食堂を開店します。タイトルの“ネコ日和”の部分は、飼い猫の「たろ」のことです。アキコは、開店と同時期に拾ったたろを、唯一の家族として迎え入れます。

© WOWOW INC.

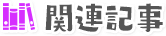
2017年6月1日
【シリーズ京都パン屋巡り行ってみた】京都で最もおいしい!?「たま木亭」
2017年5月9日
【星新一の時代小説】お金よりお米が価値を持った時代 殿さまの食卓はぬるい?
2017年1月25日
【おいしい小説】『また次の春へ』父が作った豚コマともやしのトン汁
2017年1月16日
【おいしい小説】『間宮兄弟』“ボウルいっぱいつくったフルーチェ” の誘惑
2017年1月11日
秘密のお料理代行屋の主人公が謎を解くコージーミステリ 事件の鍵はチリコンカン
2016年12月29日
【シリーズ京都パン屋巡り行ってみた】家族でゆったり週末モーニング・進々堂北山店
2016年12月14日
【おいしい小説】子供の頃にした?『きりこについて』独特過ぎる白玉の食べ方
2016年12月12日
【シリーズ京都パン屋巡り】種類豊富なサンドイッチ!ベーグル専門店Radio Bagel
2016年11月24日














