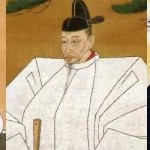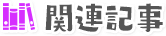【戦国武将シリーズ】信長、秀吉、家康に学ぶ現代を生き抜くためのサバイバル戦国飯
鳴かぬなら殺してしまえホトトギス、
鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス、
鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス、
言うまでもなく戦国三大武将の織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の性格を言い当てた格言です。
短い言葉の中で3人のキャラクターが的確に言い当てた名フレーズだと思います。
そんなキャラクター=人間の礎になっているものは何よりも食事であると思います。
当時の3人の食事、好物について今日は迫っていきたいと思います。
そんなキャラクター=人間の礎になっているものは何よりも食事であると思います。
当時の3人の食事、好物について今日は迫っていきたいと思います。

信長は塩辛いものを好んで食べました。
これは現代人に比べて運動量が多いので身体が塩分を必要としていたことに起因し、
薄味の料理を出すと「水の味がする!」と言って気分を悪くしていたようです。
おかずに塩辛いものを好んだ半面、白米にお湯をかけただけの飯(ミソや漬物を添える場合もある)をよく食べていました。
これは食事に時間をかけたくない、と即効性を追求した結果で信長の性格がよく表れています。
もしインスタントお茶漬けがこの時代にあったらきっと毎日食べていたんじゃないでしょうか(笑)
また、非常に甘党だったという考察もあり、干し柿が好物だったとも。
信長と言えば宣教師から金平糖をもらったエピソードが有名ですが、きっとそれも美味しく食べたんだと思います。

↑このシンプルさこそ信長の神髄?
続いて家康です。家康の強みは長寿であったこと、時期をじっと待つ辛抱強さにあります。
実際に家康は健康オタクな一面があり食事にはかなり気を遣っていたようです。
家康は粗食と知りながらも麦飯を好んで食べていました。
麦は繊維質が多く、腸内善玉菌を増やし、コレステロール・発がん物質を除去し、
さらにビタミンの合成を手伝う働きがある健康食品です。
家康は麦を食べ部下に質素倹約する領主をアピールしつつ、実はちゃっかり健康に気遣っていたのでしょう。
食事にまで表裏があるのが狸親父と言われた家康らしいと思うのは私だけでしょうか。
家康が食べ物に関する知識が豊富であったことを裏付けるエピソードは他にもあります。
関ケ原の戦いで、土砂降りの雨で火が使えず生米を食べねばならない事態になった際、
家康は「消化不良を起こすからと、コメを水に良く浸し水を完全に切ってから食べるように」と命令しました。
一方で石田三成は敗走時に空腹に耐えかねて生米を食し、腹を下して動けなくなったところを取り押さえられたと言われています。
それだけ食事に気を付けながら鯛のテンプラだけは我慢出来なかったところも家康の面白い所だと思います。

↑我慢出来なくても仕方ない!?
さて最後は秀吉です、秀吉が好んで食べたのが味噌味の焼き蛸。
蛸のタウリンは脳機能の活性化、疲労回復に効果があり、きっと秀吉の精力的な行動、
頭脳労働の助けになったであろうことは想像に難くありません。
また彼の強さでもあり個性であるのが秀吉の「人たらし」の能力です。
家康の忠臣、石川数正もそのカリスマに惹かれたのか家康の元を去り豊臣に下っています。
秀吉はいつもニコニコしていて人を惹きつける何かがあった、と当時も多くの証言が上がっています。
そんな人たらしの秘密には彼の出生が関係していると言われています。
貧乏だった秀吉はドジョウや豆味噌といったものを食べていました。
それらの食材は幸福感をもたらす脳内物質「セロトニン」の主原料トリプトファンを多く含んでいます。
セロトニンのおかげで気持ちが前向きになっている秀吉はいつもニコニコしていて人にも好かれ、人材も寄ってくる。
その上、ストレスにも強く、柔軟なアイデアも湯水のように出て来たことでしょう。
これが秀吉というキャラクターの強みであったことは言うまでもありません。

↑ドジョウ鍋。トリプトファンがグツグツです
現代でトリプトファンが入ったもの食材醤油や納豆などの大豆製品、
洋食ならヨーグルトやチーズ、バナナと言われています。
セロトニンは朝の目覚めをスッキリさせる効果もあると言われているので個人的には
それだけでも大いに摂取する価値があります。
仕事、家事、勉強…、現代社会を生きる我々は彼らとは違った形である種の戦いを強いられています。
そんな現代の戦場を生き抜くために運動量が多い日は塩分を多目にとり、麦飯を食べセロトニンの多い食事を摂る。
そうすれば天下を取った武将たちのように我々も成功を収めることが出来るのではないでしょうか?
Written by tori
その他の記事もぜひご覧ください!