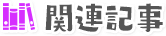土用丑の日とウナギの未来について
今年は珍しく夏に2回、土用の丑の日がありました。
皆さんはウナギは食べましたか?
江戸時代、夏に売り上げが落ちるコトをウナギ屋に相談された平賀源内が
「本日丑の日」 食すれば夏負けすることなし
と看板を立て繁盛させたことが丑の日の由来と言われています。糸井重里さんみたいですね。

またウナギには関東風と関西風で違いがあるというのはご存知でしょうか?
関東風は背開きで蒸して竹串を使います。対して関西風は腹開きで蒸さず金串を使います。
関東では切腹を連想するからと背中から包丁を入れたのに対し関西ではハラを割って話すからと腹に包丁を入れました。
ちなみに背開きのほうが腹開きより裁きやすいと言われています。
関東では気の短い江戸っ子に素早く提供できるように前もって蒸らしておいたのに対し
関西では焼きの技術でウナギを蒸さずに柔らかくしていたそうです。
関東の物に比べて噛みごたえがあると言われています。関西風は気になるので是非食べて見たい…。

しかし関西と関東のウナギの味の違いを楽しむことも近い将来出来なくなるかもしれません。
ウナギが絶滅危惧種として種の存続を脅かされているからです。
丑の日にウナギを食べる行為もその問題を加速させている点は否定できません。
では丑の日は自粛すべきなのか、普段からウナギは食べないほうがいいのか…。
それも1つ正解だと思います。
しかし同時にこの状況下でウナギを食べることが間違いだ、とも言い切れません。
美食のために生物を絶滅に追い込むのは人間のエゴ以外の何者でもありません。
しかし同時に日本人として、1つの食文化を放棄することに抵抗感を抱く気持ちも充分に理解出来ます。
どちらが正しい、どちらが間違えている、そういう問題ではないと思います。

では我々はどうするべきか。今もウナギが絶滅にさらされているこの状況を強く認識する
そして自分に何が出来るかを考える。これしかないと思います。
食べる量を減らす。料理レシピサイトで紹介されているウナギに似た食感が味わえる代用フードを食べる。
皆がそれぞれ違ったやり方でウナギのために出来ることがあるはずです。
それを意識するだけでも何かが変わるのではないでしょうか。
食べて応援!というのも1つの手段です。
ブラックジョークのようなフレーズですが、「食べて応援」を謳っている商品の中には
売り上げの一部が資源回復に使われるものもあります。
自分の手の届く範囲でいいから気をつけること、それが今我々がうなぎのために出来ることなのではないでしょうか。
Written by tori
その他の記事もぜひご覧ください!