2021年6月28日
ビニール袋にストローを差して…タイの屋台フレッシュジュースと都市伝説
ヤミー編集部からオイシイ情報をお届け!!

タイでは一般的!ジュースのビニール袋売り
タイに来たことのある人なら、現地の人がビニール袋に飲み物を入れてストローで飲んでいる姿を見たことがあるかもしれません。

タイでは袋にジュースを入れるのは一般的です。袋に氷を詰め、そこに沸かしたてのコーヒーを注いでアイスコーヒーにしたりもします。路上の飲み物屋さんでビン入りの清涼飲料水を買うと、ビンは回収され、袋に入れ替えられて渡されたりもします。タイの環境意識は日本とは大きく異なっていて、プラスチック製品が多量に消費されてきましたが、近年になってようやく環境保護を啓蒙する広報活動がみられるようになってきました。
ビニール袋売りのジュースにまつわる都市伝説…
さてさて、タイ、といえば。性転換や、いわゆる「レディーボーイ」などが日本人的には強烈な印象となっているのではないでしょうか。これは都市伝説ですが、「性別に関する多様さ(つまりレディボーイやその逆の人口の多さ)は、袋売りのジュースが原因ではないか」という話を聞いたことがあります。一時期、環境ホルモンが遠因となり東京湾のアサリの性別が一方に偏ってしまうほど生態系に影響を与えたという報道がありましたが、確かにビニール袋も環境ホルモンを出していそう…。しかもタイでは、串焼き、スープ、カレー、果ては麺類まで、テイクアウトする際には何でもビニール袋を利用します。こうしたものが体に蓄積されると…いえ、これは都市伝説に過ぎないのでしょうが。
タイでは、性別は個人の自由であるという意識が社会的に広く共有されており、男の子が女の子の格好をするであるとか、その逆も当たり前のこととして受け入れられています。ジェンダー・マイノリティーは、決して変わったことではないと認識され、好奇の目で見ることは個人の尊厳に対する冒とくに当たり、社会禁忌に反することになります。

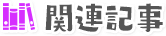
2021年2月14日
国ごとで違うバレンタイン習慣!日本から近い韓国中国のバレンタイン事情って?
2019年8月14日
【バインミー】今ベトナムがきてる!?
2019年7月1日
【バケツでビール!?】この夏行きたい一押しのお店!!
2019年3月11日
【食べてはいけない?】世界各国のご法度料理の歴史
2019年1月9日
屋台の味を家で!未だに根強いブームのチーズドッグ作ってみた。
2018年8月21日
【ザリガニ】ザリガニって本当においしいの?本音で感想をお届け【食べてみた】
2018年8月8日
何かの卵?タイで「ンゴ」「ゲーオマンゴン」と呼ばれる食材、その正体は…?
2018年7月18日
【改めて知りたい世界の3大食作法】箸のタブーとは?!
2018年7月11日















